こんにちは!!マスレコの支配人のよっしーです!
もう季節は夏真っ盛りで、8月に入ってきましたね。それと同時に吹奏楽コンクールも佳境を迎えており、残念ながら地区大会で悔しい夏を過ごしてしまった団体も数多いのではないでしょうか。
そんな中で、様々な団体を指導してきたこのよっしーが夏にやっておくと差が出る練習など少し語りたいと思います。
自己紹介
経歴:愛知県出身。現在は20代で吹奏楽指導者として活躍。過去に中学・高校・大学の吹奏楽を指導・指揮。吹奏楽コンクールにも指揮者として出場経験あり。
バンドのモチベーションを維持する
やっぱり、夏の吹奏楽コンクールなんかで一番必要となってくるのが部員やバンド全体のモチベーションですよね。
指揮者や指導者がいくら努力していても、バンドが付いてこなかったら何の意味もなさないので結果に繋がりません。
そして、コンクール目前になってようやくみんなのスイッチが入り出す…なんてのはよくあることです笑
ですが、指導者としてはこのモチベーションを維持できるかどうかというところにかかってきます。
夏休み中にこのモチベーションが下がってしまうと、冬のアンコン〜春にかけて右肩下がりに部員の士気が下がってしまいがちなので、これは何とか避けたいところですね…
過去に複数回全国大会常連校の練習を見学させていただいたことがありますが、どの団体も生徒のモチベーションが平均して高いです。もちろん、全員が高いモチベーションであるわけではないと思いますが、一部のモチベーションの低い生徒に流されないバンドの雰囲気作りが大切になってくると思います(特に中学校の現場では)。
具体的な練習計画
さて、こんな精神論ばかりでは机上の空論になってしまうので実際の練習でどのような練習をしたら良いか少しだけ考えてみましょう。
読譜力を身につけ、向上させる
4〜7月は入ってきた新入部員に対する面倒を見る暇すらほとんどなかったと思います。ですので、この8月は新入生&楽器初心者の読譜力を身につけ、2・3年生の読譜力もさらに向上させるのが大切かとおみます。近年の学校事情を拝見していると、ものすごく練習時間が減ってきているなと実感させられます。そんな中で、楽譜の読み方だったりを教える時間すらも惜しいですよね….
だからこそ、こういった夏季休暇に時間をしっかり取って読譜力を向上すれば、夏以降の練習効率もかなり上がります。そして、具体的な練習を挙げるとするならば、初見合奏です。
初見合奏の手引き
1:音源をみんなで一度だけ聴く(慣れてきたらこれは無くしてみる)
2:音を一切出さずに予見時間を5分とる(慣れてきたらもう少し短くする)
3:通す前に一度軽くチューニング
4:等倍テンポ、もしくは1/2のテンポで全体合奏(インテンポ付近で揺らすと変な癖がつく)
5:何があっても途中で止まらない
6:もう一度予見時間をとって通す(この予見も音は出さない)
7:曲に完成度は求めず、数をこなす
上記にあるのが初見合奏の具体的な手順です。経験則として、一番効果的だった練習方法がこれでした。何よりも、予見時間中の集中力を高めることが成功への近道だと思います。
また精神論のような話になりますが、強豪校ほど練習中の集中力が高い一方で、練習以外ではとっても楽しく会話を育ませています。あまり強くない学校ほど、練習中におしゃべりをして、部活の時間外でダラダラ練習をしがちです。
自分たちに厳しく、そして周りにも厳しくしなければ何も変われません。
なるべく精度の高い曲に触れる
二つ目に挙げるのは「良い曲に触れよう」ということです。別に批判するわけでないですが、M8(ミュージック・エイト)の楽曲などは、簡単かつ簡素すぎて練習曲としての選曲には適さないということです。私が意識している選曲基準はこちらです。
練習曲(エチュード)の選び方
・主旋律・対旋律・和声・伴奏の四つが明確に含まれているか
・曲の難易度はバンドに合っているかどうか
・その曲を選択することは、何がねらいなのか
大きく分けるのこの三つになるかと思います。どれも非常に重要なので、スクショ等して保存しておくことをお勧めします。
夏季休暇〜来年度の夏までのロードマップの作成
吹奏楽における年度末は7月末だと思っています。そのため、8月は新学期だと思って今後一年の活動計画を作成してください。可能であれば、生徒全体に共有することも必要かと思います。
一年の活動計画の中で、どこでどれだけのイベントに出演するのか。そして、楽器の整備や調達に必要な経費や、定期演奏会での曲目から必要経費など諸々検討するのが望ましいでしょう。
コンクールの講評を再確認
続いてしておくべきことは「コンクールの講評の再確認」です。夏コンはプロの演奏者や指揮者が審査員に入ります。そんな方々が感じた第三者的な意見をしっかりと受け止めることが必要です。
よくあるコメントとして「音程」、「調性」、「和声感」の指摘などが多いのではないでしょうか?
そういったコメントに対して、真摯に向き合うことで来年の夏が華々しくなるでしょう。
最後にひとこと
ひとまず、みなさん吹奏楽コンクールお疲れ様でした。結果はどうであれ、努力したという過程が最も大切だと言えます。その過程があることで、来年への活力にも繋がりますし、今後のみなさんの音楽人生がより豊かになることでしょう。
このブログでは、ちょくちょくこういった吹奏楽関連の記事をまとめていますので、よろしければ他の記事もご覧ください!
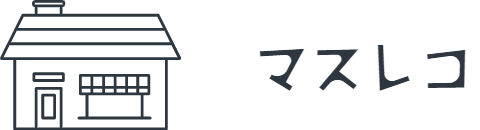



コメント